阿波紙の起源については、忌部氏の一族の斎部広成(いんべのひろなり)という人が『古語拾遺(こごしゅうい)』(807)という忌部族に関する記録を書き残しています。その文中には「天日鷲命(あめのひわしのみこと)(阿波忌部族の祭神)が阿波国に来て(約
1300年前)アサ、コウゾを植え、紙や布の製造を盛んにした。その地を麻植(おえ)郡といい、今にその子孫が住んでいる。天皇が即位される時に執り行なわれる天地の神々を祭る大嘗祭(だいじょうさい)には、その子孫が荒妙(あらたえ)(麻の織物)を奉る」とあります。
江戸時代には、幕府が各藩に産業を盛んにするように命じたので、各藩に特産物ができました。阿波の特産物は四木三草といって、四の木はコウゾ、クワ、チャ、ウルシであり、三草はアイ、サトウキビ、タバコです。その中でもアイと紙は全国的に売れ、藩の財政を潤しました。 |
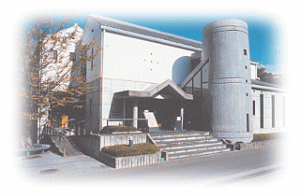 |
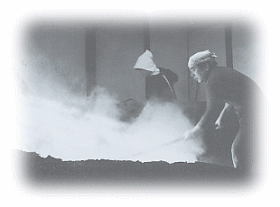 |
明治時代には、徳島県でも紙を漉く家が500軒もあり、そのうちの200軒が麻植郡山川町にありました。楮紙や雁皮紙を中心にした数多くの種類の和紙を漉き分け、パリの万博に出展したりして全盛の時でした。
戦後は和紙の受難期で、大きな変革を余儀なくされました。当然阿波和紙も製造軒数においては衰退の一途をたどるばかりで、現在では4戸ほどになりました。しかし、その間に伝統的工芸品産業の指定(
1976)、(財)阿波和紙伝統産業会館の設立(1988)などの事業を執り行ない、阿波和紙の普及に尽くしています。
阿波和紙の活動の中心である(財)阿波和紙伝統産業会館(アワガミファクトリー)では、以下のような活動をしています。
①アーティスト、デザイナーのために工房を開放し、作品の制作を援助しています。
②和紙に関する資料をととのえ参考に供しています。
③実技指導および手漉き和紙研修会を行ない、後継者の育成の援助をしています。 |
|